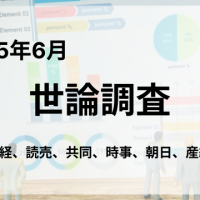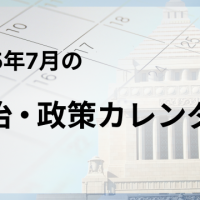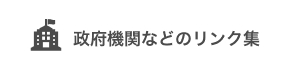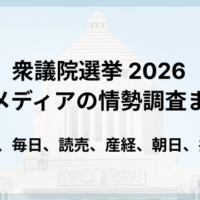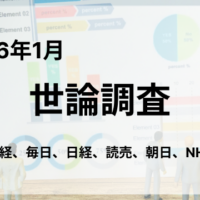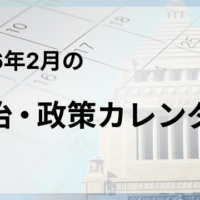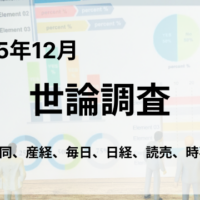国際連携で情報ギブ・アンド・テイク
政府始動、カギ握るサイバー統括室 机上演習でシナリオに沿い模擬実験
病院や金融機関といった重要インフラに対するサイバー攻撃の増加を踏まえ、先の通常国会で「能動的サイバー防御関連法」が成立した。官民連携の下、平時から通信を監視して攻撃兆候を把握し、警察や自衛隊が海外の敵拠点へ先制的に対処することで被害を防止する。いわば「攻めの防御」であり、日本のサイバー防衛は先進諸国へのキャッチアップを目指し、新段階に入った。7月1日、政府は司令塔となる「国家サイバー統括室」を発足。本格的な体制作りが始まっている。
自民党サイドで法策定に尽力したのが大野敬太郎・党政調副会長(党経済安全保障推進本部幹事長)だ。東京工業大(現東京科学大)大学院を修了後、大手企業で宇宙事業などに従事し、東大で博士号を取得。これまで防衛政務官、内閣府副大臣などを歴任した。安全保障とテクノロジーという切り離せない二つの領域に通じた政界有数の理系人材に、取り組みの状況を聞いた。
大野敬太郎氏の発言のポイント
・日本はサイバー攻撃被害が顕在化し対処は喫緊課題
・国際的に2014年のウクライナ戦争で攻撃が劇的変化
・能動的サイバー防御法により国内被害を防御し脅威排除
・体制と運用ルールの整備、人材育成、官民連携が重要
・担当閣僚の明確な意思が司令塔をうまく機能させる
・能動的サイバー防御の能力保有で国際連携拡大
※聞き手:政策ニュース.jp編集部
インタビューは2025年6月20日に実施しました
マルチドメインに対処できる安全保障
― 先の通常国会で能動的サイバー防御関連法が成立したが、その意義について。
(大野敬太郎氏)わが国ではサイバー攻撃の被害が顕在化しており、対処はまさしく喫緊の課題だ。国民の皆様の目線から見て、私ども国会議員への要請でもあったと認識している。一方、国際社会から見た場合、起点となったのは2014年に勃発したウクライナ戦争だ。戦い方や攻撃が劇的に変わったというのが、安全保障関係者の共通の理解であった。このようなマルチドメインの戦いに対処しなければいけないという安全保障上の要請に従って、各国はサイバー防衛について、かなりアップデート、アップグレードした。
しかし、日本は他国に比べ、必要な対応に大きく遅れを取っていた。自民党は従前、能動的サイバー防御の体制整備を求める提言を政府に出していたが、いよいよこのままではいけないとの認識が高まった。そこで、小林鷹之元経済安全保障担当相らとともに、党内で、サイバー防御、経済インテリジェンス、機密情報へアクセスする人の信頼性を認証する「セキュリティー・クリアランス」の3点について、具体的な実装方法も含めて提言をまとめ、政府に要請した。こうした経緯で、現在に至っている。従って、実体的な国内の被害の防御とともに、安全保障上の脅威も排除できるという、極めて有意な状態になったと考えている。
IoT機器とデータ利活用
― 成立した法律に従い、具体的にどのように取り組みを進めるのか。
(大野氏)ざっくり言うと、まずは体制を整備し、その後、運用面でのルールを細かく整えていく必要がある。運用面において一番重要なのは人材であり、官民の連携だ。この在り方をうまく構築できるかどうかで、防御の仕組みがきちんと機能するかどうかが決まるといっても過言ではない。法律ができても、まだ実態はなく、これからが本番と言える。制度ができても、それだけで防御できるものではないためだ。
同時に、周辺を含めての整備が不可欠となる。その一つは、センサーや通信機能の安全性を担保することだ。ネットワークに接続されることで外部のデータを送受信し、他の機器やシステムと連携して機能する機器(IoT機器)の標準化が必要だ。これは政府が既にガイドラインなどを施行している。IoT機器が安全なものかどうかを独立行政法人情報処理推進機構(IPA)で認証する仕組みも導入しているが、その範囲を機器だけでなくサービスにも拡大するよう検討すべきだと思う。また、データを利活用することで、さまざまな利便性が高まる一方、その裏側ではリスクもある。データ流通の健全化に向け、取り組みには足りない部分がまだある。こうした面でも十分なものとなるように努力していきたい。
テーブル・トップ・エクササイズで実践
― 人材育成について詳しく聞きたい。
(大野氏)基本的には知見ある諸外国の皆さんとの交流から始まると思う。一方で、国内には民間で、いわゆるホワイトハッカーと呼ばれる高度な知識と能力を持った方がおられる。そういった方も含め、既に能力を持った方々との交流促進が重要となる。同時に実践も必要だ。これはテーブル・トップ・エクササイズ(TTX)と呼ばれている机上演習によって、シナリオを実際に作り、それに従って模擬実験を繰り返し行うことで技能を向上させる方法がある。また、今回の法律に基づいてインシデントを共有しなければいけない企業の担当者の方々と、一緒になって能力構築を進めることも大切。トレーニングプログラムをしっかり充実させていくことになると思う。
― 人工知能(AI)の進歩は著しく、能動的サイバー防御への活用促進は不可欠だ。
(大野氏)まだ体制整備という入り口の段階に差し掛かったところではあるが、これから運用面のさまざまな課題に挑戦する中で、AIの導入は確実に目指すことになると思う。サイバー攻撃に対する基本的な対処手法は、通常と異なる通信の流れを察知し、それを追跡するというものだが、今はこれを人的に行っている。こういう作業は、まさにAIのツールを使って効率化できる部分だ。これを能動的防御である無害化にどのように役立てるのかという点は、一つの検討課題だと思う。ただ、まずは受動的防御の側面、具体的には情報分析へのAIの活用に注力していくことになると思う。
組織に「魂」を入れる
― 司令塔となる「国家サイバー統括室」は各官庁から人材を集めることになる。人事的融和など課題は多いと思うが、どのような点に留意すべきか。
(大野氏)どの組織でも重要なことは、全体のトップが政治的に責任を取れる体制をつくった上で、そのトップが十分に理解して、しっかり判断できるということに尽きると思う。例えば日本政府には国家安全保障局(NSS)という組織がある。首相を社長に例えると、NSSは社長秘書室みたいなものだ。そして首相自身がその意思を明確に示して運営しているうちに、NSSはかなりしっかりした組織になった。 各官庁もそうした認識を持つようになり、エース級の人材を送ってくるので、極めていい動き、機能を果たしている。
担当閣僚である平将明デジタル相は、当然のことだが明確な意思があり、理解力は折り紙付きだ。国家サイバー統括室に魂を入れていただけるのは間違いない。そうして新組織がうまく稼働するようになって、他省庁も「協力することは当然だ」と思うような形になるまで昇華させることが必要だ。
「日本も能力」と諸外国に認識される価値
― 能動的サイバー防御の効果的な実行には、脅威の手掛かりとなる情報の収集力を高めることが求められる。
(大野氏)法律の施行はまだ少し先になり、通信モニタリングは2026年から開始するので、今から直ちに情報収集活動が始まるわけではない。ポイントは、やはり国際連携できる立場になったということだ。つまり、日本も能動的サイバー防御の能力を持ち、そのために民間の情報を集めることができるようになったという認識を、諸外国に持ってもらえるようになった。この価値は大きい。
ご承知の通り、非常に多くの事業者によるさまざまな通信が日本を通っている。そして、機械的なスクリーニングではあっても、そういった事業者から日本政府に情報を提供していただくことになる。海外から見ると、日本を通過する情報は、日本政府が取得することができるという認識を持つことになる。そうすると、情報の世界はギブ・アンド・テイクなので、他国との情報の共有や分析の幅が広がる。これにより、質はかなり向上すると思う。
関連リンク
・大野敬太郎オフィシャルサイト – プロフィール、活動報告、基本政策など
・衆議院議員 大野 敬太郎(おおの けいたろう) – 経歴、関連ニュースなど。自民党
・サイバー安全保障に関する取組 – 能動的サイバー防御関連法の説明資料など。内閣官房
関連記事
・【能動的サイバー防御関連法案が5月にも成立】
法案の意義や修正の狙いはー自民、立憲、維新3党の責任者に聞く(2025年4月24日)
・「能動的サイバー防御」有識者会議、論点を整理(2024年8月8日)
【インタビュー】
・元陸上自衛隊システム防護隊長・伊東寛氏(2025年4月22日)
・西貝吉晃・千葉大大学院社会科学研究院教授(2025年3月19日)
・茂田忠良・日本大危機管理学部元教授(2025年3月10日)