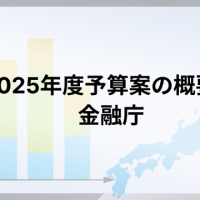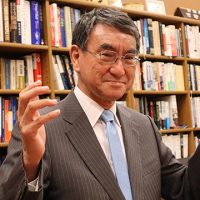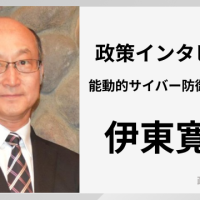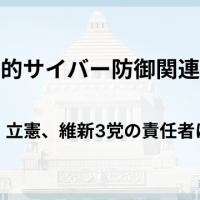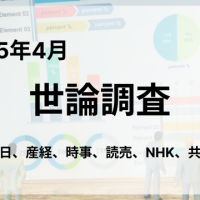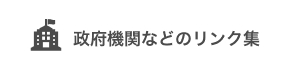プライマリー・バランスは単なる結果論
― 年収の壁の引き上げが焦点となっている。
年収の壁の引き上げは、178万円までがふさわしいかどうかはともかく、行うべきだ。経済では国民の個人消費が最も大きく、それを拡大するには手取りを増やさねばならない。給料アップは大事だが、減税でも手取りは増える。仮に178万円に引き上げると8兆円ぐらい財源が必要だと言われているが、それは国債で賄えばよい。毎年、全体で手取りが8兆円増えれば消費が拡大し、取引や所得の増加につながり、税収増となる。
予算の財源は税でなくとも通貨発行、つまり国債で全部できる。そして国債発行により財政出動したお金を税金として回収するわけだ。これを1年間トータルで見ると、歳出と税収が同じくらいになる場合もあるし、税収が歳出を上回る年もあれば、歳出が多くて税収が少ないこともある。経済状況により変わるだけだ。こう考えるとPBが黒字か赤字かは単なる結果論にすぎない。何の意味もないことに30年も固執している。
― 政策は財源とセットで議論されることが多い。
財源を先に論じるのではなく、指標として物価上昇率や投資額に注目するのが正しい。それらが大きくなる方向で進むことが必要だ。そして拡大しすぎたと判断したら、財政破綻を懸念するのではなく、経済が極端にインフレになることを防ぐために金利や税率を引き上げたり、予算執行額を減らしたり、さまざまに調整できる。
高名学者もミスリード
― 政府の財政政策が根本的に変わらない理由は。
一つは単純な間違いだ。知らなかったり勘違いしていたりというのもあると思う。しかし、何十年も大間違いをしておいて、誤りだと分かっても今さら直せないというのは断じて容認できない。もっとも、政治家も間違っていたのであり、財務省だけを責めてもかわいそうだ。私自身も誤りに気付いていなかったが、「何かおかしい」と思い調べていくと事実が分かり、十数年前から今のような主張を始めた。ただ、そういう事実や理論、考え方を教えている所はなかったので、気付かなくても仕方ない。
そもそも大学や研究者も「予算は税収の範囲内でつくるべきだ」と信じ込み、経済の実態やお金が回る本当の仕組みを正しく教えていなかった。それどころか「国債による財政拡大は無責任」といった言説は現在もあふれている。財務省の顧問的な立場で発言している著名な学者の話などを聞いても「いったい何を言っているのか」と首をかしげることがある。
― 「常識」が誤りだったということか。
例えば「銀行はどうやってお金を貸すのか」という経済の基本事項について、高名な大学教授でも間違った記述をしていることがある。「銀行は、皆さんが預けた預金を元にお金を貸し出している」と書いている。有名な先生の教科書なので、みんなそう思い込んでいるが、事実は逆だ。銀行は預金を集めてから、それを貸し出しに回すのではない。返済能力のある借り手から借用証書を取り、預金通帳に貸出額を記入するだけで、貸し出しを行っている。預かったお金の何倍もの額を、通帳記入だけで融資しているわけだ。これが「信用創造」。
そして、政府による国債発行も同様に信用創造だ。政府が国債を発行し、それで得た資金を予算として公共事業・サービスなどで執行すれば、そのお金は民間側の預貯金に回る。民間つまり国民は、その預貯金で物を買ったり、サービスを受けたりする。まとめると、国民の預貯金が増えるのは、銀行から借り入れしたときか、政府が国債を発行したときとなる。大切なのは、信用創造は最初から相当の財源がなければできないわけではなく、財源の制限を受けない「無から有を生み出す道具」と言えるわけだ。
「火あぶり」になっても地動説
― もう少し詳しく。
学者や官僚はよく「民間に国債を買ってもらうと国民の預貯金を減らすので、景気が上向いて民間側が進んでお金を使おうとしても、出回っているお金の量が減っているから金利が上がって経済に悪影響を与える。よって財政出動や公共事業はそれほど効果がない」という説明をする。こういう誤りは「国民の預貯金から貸し出すので、結果的に金利を上昇させる」という前提で考えることから生じる。信用創造とは「何もないところから負債と資産が出てくる仕組み」ということを理解していない。
また、民間企業であれば借入金は銀行に返済せねばならないのに対し、政府の借入金である国債は償還期限が来ると、新たに「借り換え債」を発行して差し替えるだけであり、事実上返済していない。さらに先に述べた通り、国債残高の半分を日銀が保有しているため、利払い費の半分は政府に戻って来ている。財政破綻のしようがない。
― 財政政策の転換はあり得るのか。
政府はこうした事実に目を向けず、誤った政策に固執している。しかし、例えて言うと、最初は太陽が地球の周りを回っているとする「天動説」が唱えられていたが、地球が太陽の周りを回る「地動説」が正しいと改めた「コペルニクスの転換」の歴史がある。地動説に変わるまで何百年かかったことも、日本の状況とよく似ている。忘れてはならないのは、地動説を主張していた人は、それが認められるまで迫害され、大量に火あぶりで処刑されていったことだ。これも今のわが国のようだ。
国民の血税を大切に使うモラルは必要だが、科学的事実と倫理は分けて考えなければならない。本当の優秀さとは、教科書を理解する頭脳だけではなく、同時に現実を見て自分で解決策を考え出せることだ。政治家や官僚、学者は自分が教わった学説を一方的に信じているだけではいけない。
関連リンク
・西田昌司 – 経歴、関連ニュース、公式サイトへのリンクなど。自民党
2